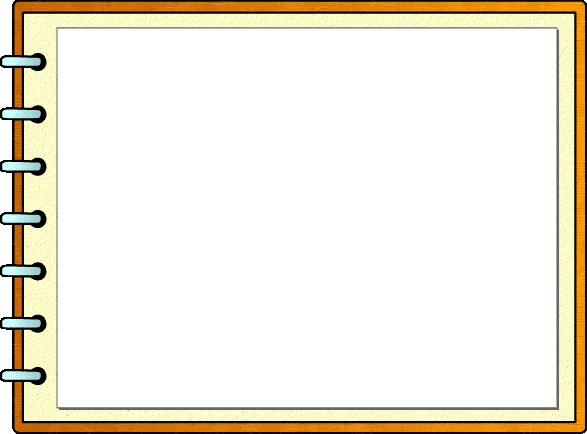
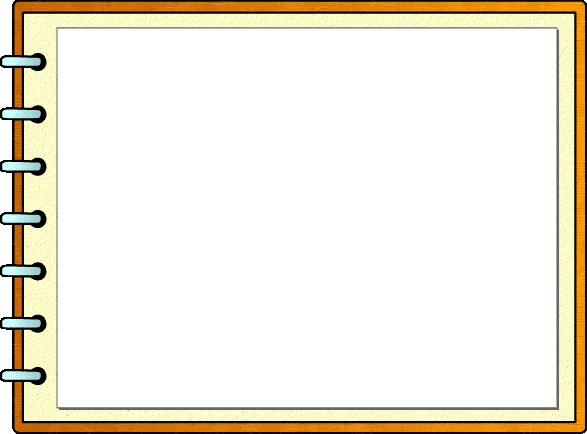
| �y��ʁz�玙�E���x�Ɩ@����������܂� �@ �@���q����̊ϓ_����玙�x�ƁE���x�Ɩ@����������܂����B �A�ƋK���̕ύX�ȂǁA�{�s���܂łɑΉ����K�v�ł��B�����玙�E���x�Ɩ@�̊T�v�͈ȉ��Ƃ���ŁA�i�K�I�Ɏ{�s����܂��B �@ �w�玙�E���x�Ɛ��x�̕ύX�x �@�@(�P)�R�܂ł̎q��{�炷��J���҂̒Z���ԋΖ����x�y�я���O�J���̖Ə��̋`���� �@�@�@�@�@�J���҂���]����Η��p�ł���Z���ԋΖ����x(�P���U����)��݂��邱�Ƃ��`���� �@�@�@�@�A�J���҂��琿�����������Ƃ��̏��莞�ԊO�J���̖Ə��𐧓x�� �@�@(�Q)�q�̊Ō�x�ɂ̊g�[ �@�@�@�@���w�Z�A�w�O�̎q���A�P�l�ł���ΔN�T��(���s�ǂ���)�A�Q�l�ȏ�ł���ΔN�P�O�� �@�@(�R)�j���̈玙�x�Ǝ擾���i��i�p�p�E�}�}��x�v���X���j �@�@�@�@���ꂪ�Ƃ��Ɉ玙�x�Ƃ��擾����ꍇ�A�P�Q����(���s�P��)�܂ł̊ԂɁA�P�N�Ԉ玙 �@�@�@�@�x�Ƃ��擾�\�Ƃ��� �@�@(�S)���x�ɂ̑n�� �@�@�@�@�v����Ԃ̑ΏۉƑ����A�P�l�ł���ΔN�T���A�Q�l�ȏ�ł���ΔN�P�O�� �@�@�{�s�G�����Q�Q�N�U���R�O���E�E�E��L(�P)�A(�S)��100�l�ȉ��̊�Ƃɂ��Ă͕����Q�S�N�\�� �@ �w�����玙�E���x�Ɩ@�̎������̊m�ۑ[�u�|�P�x �@�@���玙�E���x�Ɩ@�ɌW��J���҂Ǝ��Ǝ�̊Ԃ̕����Ɋւ��钲��x�̑n�� �@�@�{�s�G�����Q�Q�N�S���P�� �@ �w�����玙�E���x�Ɩ@�̎������̊m�ۑ[�u�|�Q�x �@�@�����Ǝ�ɂ����̎���I�����y�ѓs���{���J���ǒ��ɂ�镴�������̉������x�̑n�� �@�@���@�ᔽ�ɑ����Ɩ��̌��\���x�A�����߂��ꍇ�̖����̉ߗ��̑n�� �@�@�{�s�G�����Q�P�N�X���R�O�� �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�ܗ^�x���͂̒�o�ɂ��� �@ �@�ܗ^�̌��N�ی�������N���ی��̕ی����́A�W���ܗ^�z�ɕی��������|���Čv�Z���܂��B �ܗ^���x�������ۂɂ͏ܗ^�x���͂��o���A�ی������v�Z����W���ܗ^�z�̌�����s���܂��B �ܗ^�x���͂̒�o�����́A�x��������T���ȓ��ł��B �ܗ^�̎x�������I�������A�����Ɏx���͂̍쐬�E��o������悤�ɂ��܂��傤�B ���łɏܗ^�x�����I����Ă��鎖�Ə��͎x���͂̒�o��Y��Ă��Ȃ����m�F���Ă��������B �@ ���ܗ^�̎x�����Ȃ��ꍇ�ł��͏o�͕K�v�ł��B �@�ܗ^�͏o�̏��ނ��͂��܂�����x�����т��Ȃ��ꍇ�ł��͏o�����o���Ă��������B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w�ܗ^�x���́x�̏ڍ׃y�[�W �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz�Œ���������肳��܂� �@ �@�����Q�P�N�P�O���Q�T����茧�̍Œ���������Ԋz�V�W�X�~�i�Q�R�~�t�o�j�ɉ��肳��܂��B �����̏�p�E�Վ��E�p�[�g�E�A���o�C�g���S�Ă̘J���҂ɓK�p����A���̋��z�ȏ�̒������x�����K�v������܂��B���^�v�Z�Ȃǂ̍ۂ͏[�����ӂ��Ă��������B �@ ���Œ�����̓K�p���O�K�肪�p�~����A���z����ƂȂ��Ă��܂��B �@�Œ�����̌��z�������Ȃ��ׂɂ͎��O�Ɍ��z���ዖ�̐\�����K�v�ł��B �@���z�̑Ώۂ͇@���_���͐g�̂̏�Q�ɂ�蒘�����J���\�͂��Ⴂ�҂ƁA�A�f���I�J���ɏ]������ �@�҂Ƃ���Ă���A���z�̗��R�����m�ɂȂ��Ă���K�v������܂��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z���{�Ǐ����N�ی��E�����N���̕ی��������ύX����܂� �@ �@�����Q�P�N�X����(�P�O���[�t������)��萭�{�Ǐ����N�ی��̌��N�ی��������ύX����܂��B �_�ސ쌧�̌��N�ی������͈ȉ��̂Ƃ���ł��B �����Q�P�N�X���ȍ~�G�W�D�P�X���i���݂W�D�Q�O�����S���ꗥ�j �@ �s���{�����̕ی����z�\�����J����Ă��܂��̂������ۂ̂g�o�ł��m�F�������B �@��N�Ɠ��l�ɕ����Q�P�N�X����(�P�O���[�t��)�������N���ی��������O�D�R�T�S�������グ ���܂��B�@�����ɂ������N���̕ی������͕����Q�X�N�܂Ŗ��N���肳��܂��B ��ʔ�ی��҂̏ꍇ�E�E�E �����Q�P�N�X���ȍ~�G�P�T�D�V�O�S���i���݂P�T�D�R�T�O���j �@ �����N���̕ی����z�\�͎Љ�ی����̂g�o�ł��m�F�������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz��ʘJ���Ҕh���Ƃ̋�����ς��܂� �@ �@�h�������Ǝ�ɂ��K���Ȍٗp�Ǘ������I�Ȏ��Ɖ^�c�̊m�ۂ�}�邽�߁A��ʘJ���Ҕh�����Ƃ̋�����ύX����܂��B�ύX�����͎̂��Y�v���Ɣh�����ӔC�҂̗v���ł��B �V�K���͕����Q�P�N�P�O���P���\�������A�X�V�͕����Q�Q�N�S���P���ȍ~���K�p�ƂȂ�܂��B �@ �w��ȉ����̓��e�x �@�P�D���Y�I��b�ɌW��v���i���Y�v���j �@�@�P���Ə������� �@�@�@������Y�z(���Y�z�|���z)�@�P�C�O�O�O���~�@���@�Q�C�O�O�O���~ �@�@�@�������E�a���̊z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W�O�O���~�@���@�P�C�T�O�O���~ �@�Q�D�h�����ӔC�҂ɌW��v�� �@�@(�P)�h�����ӔC�҂̌ٗp�Ǘ��ɌW��v�� �@�@�@�u�ٗp�Ǘ��o�����R�N�ȏ�̎ҁv�݂̂Ƃ���B�ȉ��̂Q�̗v�����폜�B �@�@�@�u�ٗp�Ǘ��o���{�E�ƌo���v�̊��Ԃ��T�N�ȏ�̎ҁ@���폜 �@�@�@�u�ٗp�Ǘ��o���{�h���J���҂Ƃ��Ă̋Ɩ��o���v�̊��Ԃ��R�N�ȏ�̎ҁ@���폜 �@�@(�Q)�h�����ӔC�ҍu�K�̎�u�ɌW��v�� �@�@�@���\�����O�u�T�N�ȓ��̎�u�v�@���@�u�R�N�ȓ��̎�u�v �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�֘A�߰�ނցl�J���Ҕh������ �@�@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���ی��z�N�x�X�V�ɂ��� �@ �@�J���ی����͑O�N�x�Ɏx����ꂽ���^�����ƂɁA���N�x�̊T�Z�ی����y�ёO�N�x�̊m��ی������Z�o���A�ی����̐��Z���s���܂��B���̎葱��N�x�X�V�Ƃ����܂��B �{�N�x���J���ی��̔N�x�X�V�葱(�ی����̊T�Z�E�m��\������є[�t)�̎������ύX����܂����B �Љ�ی��̎Z���b�葱�̊��ԂƏd�Ȃ�܂��̂ŏ��ނ��͂����瑬�₩�Ɏ葱�����K�v�ł��B �@�@�y�\�������z�@�U�^�P�`�V�^�P�O�@�i�����Q�O�N�x�܂łS�^�P�`�T�^�Q�O�j �@�@�y�[�t�����z�@��P���i�ꊇ�j�G�V�^�P�O�@��Q���G�P�O�^�R�P�@��R���G���N�P�^�R�P �@ �J���ی��̕ی����̎Z��̍ۂɂ́A�O�N�x(�S���P������R���R�P���܂ł̂P�N��)�̋��^�䒠�E���^�x�������Ȃǂ̏������K�v�ƂȂ�܂��B �N�x�X�V�葱�͓��������ł��戵���Ă���܂��̂ŁA���˗��̏ꍇ�͂����߂ɂ����k���������B �@ ���J�Еی������E�ٗp�ی��������ύX�ƂȂ��Ă��܂��̂ł����Ӊ������B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�֘A�߰�ނցl�N�x�X�V �@�@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�Z���b�͂ɂ��� �@ �@�Љ�ی��̕�V���z�Z���b�͂̒�o�������߂Â��Ă��܂����B �Љ�ی�(���N�ی��E�����N���ی�)�̕ی����́A��Ђ��e�]�ƈ��ɑ��Ďx���������^���猈�肳�ꂽ��W����V���z������ƂɎZ�o���܂��B�W����V���z�͂������̓����ɋ敪����Ă��܂��B �����⏸�i�Ȃǂɂ�鋋�^�����̕ω��ɑΉ����邽�߁A���N�͏o���s���A���̌�P�N�Ԃ̕W����V���z�����肵�܂��B���̎葱���Z���b��(�莞����)�Ƃ����܂��B �@ �͏o�̑Ώۂ́A���N�V���P�����݂̎Љ�ی���ی��ґS���ƂȂ�܂��B(�U�����i�擾�҂�����) �Љ�ی����������X������鎑�����Q�l�ɂ��đ��߂ɍ쐬���܂��傤�B ��o���Ԃ͂V�^�P�`�V�^�P�O�ƂȂ�܂��̂ŖY�ꂸ�ɒ�o���Ă��������B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�֘A�߰�ނցl�莞����E�Z���b �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�ܗ^�x���͂̒�o�ɂ��� �@ �@�ܗ^�̌��N�ی�������N���ی��̕ی����́A�W���ܗ^�z�ɕی��������|���Čv�Z���܂��B �ܗ^���x�������ۂɂ͏ܗ^�x���͂��o���A�ی������v�Z����W���ܗ^�z�̌�����s���܂��B �ܗ^�x���͂̒�o�����́A�x��������T���ȓ��ł��B �ܗ^�̎x�������I�������A�����Ɏx���͂̍쐬�E��o������悤�ɂ��܂��傤�B ���łɏܗ^�x�����I����Ă��鎖�Ə��͎x���͂̒�o��Y��Ă��Ȃ����m�F���Ă��������B �@ ���ܗ^�̎x�����Ȃ��ꍇ�ł��͏o�͕K�v�ł��B �@�ܗ^�͏o�̏��ނ��͂��܂�����x�����т��Ȃ��ꍇ�ł��͏o�����o���Ă��������B �@ �ߋ��ɂ�����ܗ^�͏o�̓͏o�R���͏o���e�̌��͂���܂��H �����P�T�N���Љ�ی����̎Z�o�ɂ͑���V������������A�ܗ^(�{�[�i�X)�ɂ����^�Ɠ����ی������������ĕی����S���邱�ƂɂȂ�܂����B�]�ƈ��̕��̔N���z�ɂ��e��������܂��̂ŏܗ^�͏o�̖���o���肪�Ȃ����m�F�����肢���܂��B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�֘A�߰�ނցl�ܗ^�x���� �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�ٗp�ی��z���i�擾�͂̂U�����ȏ�̒x��ɂ͒x�����R�����K�v �@�ٗp�ی��̎��i�擾�̓͏o�͌ٓ���̗����P�O���܂łƂȂ��Ă��܂��B ����܂œ͏o�����ɒx�ꂽ�ꍇ�͎��Ǝ傩��̒��擙�Ŋm�F���k���Ẳ������������Ă��܂������A�啝�Ȓx���͘J���҂̕s���v�ƂȂ�ꍇ�����邽�߁A���L�̗v�̂Œx�����R���̒�o����߂��܂����B �@����o�������U�����ȏ�o�߂����ꍇ�@�E�E�E�@�x�����R����Y�t �@����o�������R�����ȏ�o�߂����ꍇ�@�E�E�E�@�����䒠�E�o�Ε��Y�t(�]���ǂ���) �@ �ٓ���̗����P�O���܂łɖY�ꂸ�Ɍٗp�ی��̎��i�擾�葱���s���ĉ������B���p���Ԃ̎҂ɂ��Ă����p���Ԃ��܂ߌٓ��������ٗp�ی��ւ̉������K�v�ł��B �������v���̊ɘa�ɂ��Z���Ԍٗp�J���҂łU�����ȏ�ٗp�����ꍇ�͉������K�v�ł��B �@(�]���͂P�N�ȏ�B�ڍׂ͉��L�Q��) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�֘A�߰�ނցl�ٗp�ی� �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�ٗp�ی��z�ٗp�ی����x����������܂� �@���݂̌������ٗp���Ə�܂��ٗp�ی����x����������܂����B(�����Q�P�N�R���R�P�����) �ٗp�ی��̓K�p�͈́A��{�蓖�̎v���̊ɘa�ȂǑS�Ă̎��Ǝҗl�Ɋ֘A���鎖��������܂��̂ő��߂ɉ������e�̊m�F�����肢���܂��B �@ �@�y��ȉ��������z �@�@�@�P�D�ٗp�ی��̓K�p�͈͂̊g�� �@�@�@�Q�D�K�J���҂ɑ����{�蓖(���Ƌ��t)�̎v�����̊ɘa �@�@�@�R�D�ďA�E������ȕ��ɑ��鋋�t�����̉��� �@�@�@�S�D�ٗp�ی������̈��������E�E�E�ʋL�Q�Ɓ@�@�@�Ȃ� �@ �P�D�ٗp�ی��̓K�p�͈͂̊g�� �@�Z���ԏA�J�ҋy�єh���J���҂̌ٗp�ی��̓K�p����ȉ��̂悤�Ɋɘa����܂��B �@�@�@���G���P�N�ȏ�̌ٗp�����݂����邱��(�T����J�����ԂQ�O���Ԉȏ�) �@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�V�G���U�����ȏ�̌ٗp�����݂����邱��(�T����J�����ԂQ�O���Ԉȏ�) �@ �@�����Q�P�N�S���ȍ~�ɉ�����̊�����J���҂��ٓ��ꂽ�ꍇ�͌ٗp�ی��̎��i�擾���K�v �@�ł��B�S���ȑO����Ζ����Ă���J���҂��S���ȍ~��������ƂɂȂ����ꍇ�����l�ł��B �@ �Q�D�K�J���҂ɑ����{�蓖(���Ƌ��t)�̎v�����̊ɘa �@�J���_�X�V����Ȃ��������Ƃ��̑���ނȂ����R�ŗ��E���ꂽ���̎v�����ȉ��� �@�l�Ɋɘa����܂��B �@�@�@�����E���ȑO�P�N�Ԃɔ�ی��Ҋ��ԂU�����ȏ�E�E�E�ʏ�͂Q�N�ԂɂP�Q�����ȏ� �@ �@�܂��A�J���_�X�V����Ȃ����Ƃɂ�藣�E���ꂽ���́A��{�蓖�̏��苋�t����������� �@���i��(�|�Y����قȂǂŗ��E���ꂽ��)�Ɠ��l�Ɏ�����Ȃ�܂����B �@ �R�D�ďA�E������ȕ��ɑ��鋋�t�����̉��� �@������i�҂�J���_�X�V����Ȃ����Ƃɂ�藣�E���ꂽ���ŁA���̗v���ɊY�����A �@���ɍďA�E������ƌ����E�ƈ��菊�����F�߂��ꍇ�͋��t�������U�O������������܂��B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�֘A�߰�ނցl�ٗp�ی� �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�ٗp�ی��z�ٗp�ی����������肳��܂��� �@�ٗp�ی������P�O�O�O���̂S�����������邱�Ƃ��R�����Ɍ��肵�܂����B �V�����ٗp�ی����ɂ͕����Q�P�N�S������ύX�ƂȂ�܂��B �@ �����Q�P�N�x�ٗp�ی�����
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J�Еی��z�J�Еی������ύX����܂��� �@�����Q�P�N�S���P�����J�Еی������ύX�ɂȂ�܂��B �����Q�P�N�x�̊T�Z�ی����͐V�����J�Еی������A�����Q�O�N�x�̊m��ی����͍��܂ł̘J�Еی������g�p���邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA�N�x�X�V�̍ۂɂ͏[�����C�������������B ���Ƃ��c�ޕ��͘J������ύX�ƂȂ������Ƃ̎�ނ�����܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B �J�Еی����͑S�z���Ǝ啉�S�̂��ߋ��^�T���z�ɂ͕ύX����܂���B �ڂ����͔N�x�X�V�̍ۂɑ��t����鎑�������m�F���������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�֘A�߰�ނցl�J�Еی� �@�@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z���ی��������ύX����܂��� �@�����Q�P�N�R����(�S���[�t������)��萭�{�Ǐ����N�ی��̉��ی��������ύX����܂��B ����ی����̌v�Z������ꍇ�ɂ͒��ӂ����ĉ������B �@�����Q�P�N�R���ȍ~�G�P�D�P�X���i���݂P�D�P�R���j ���^�T���͗��������̏ꍇ�͂S�����̋��^����ύX�ƂȂ�܂��B �Ȃ��A�����N���ی��̕ی������ɂ͕ύX������܂���B �ڂ����͕ی����z�\�ł��m�F���������B�Љ�ی����̂g�o�ȂǂɌf�ڂ���Ă��܂��B �@ �����N�ی��g���ɉ�������Ă�����̕ی������͑g���ɂ���ĈقȂ�܂��̂Ŋm�F���Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���Ǘ��z�J����@���ꕔ��������܂� �@�����ԘJ���̗}���A�J���҂̌��N�m�ۂȂǂ�ړI�Ƃ��ĘJ����@�̈ꕔ����������܂��B �����Q�O�N�P�Q���P�Q���Ɍ�t����A�����Q�Q�N�S���P������{�s����܂��B ���������A�L���x�ɂȂNJ֘A������e������܂��̂ŁA���e���m�F�����߂̑Ή����K�v�ł��B �@ �@�@�@�y�����̃|�C���g�z �@�@�@�@�P�D���ԊO�J���̊����������̈����グ �@�@�@�@�Q�D�������������グ��w�͋`�� �@�@�@�@�R�D�N���L���x�ɂ����ԒP�ʂŎ擾�\ �@ �P�D���ԊO�J���̊����������̈����グ �@�P�����U�O���Ԃ��z���鎞�ԊO�J���ɂ��Ă͊��������Q�T������T�O���Ɉ����グ���܂��B �������A������Ƃ͓����̊ԏ�L�����グ�͗P�\����܂��B �@�܂��A�J�g���c�ɂ���L�����グ���̊��������̎x���ɑウ�āA�L���x�ɂ̕t�^�őΉ����邱�Ƃ��o���܂��B(�]���̊����Q�T�����̎x���͕K�v�ł�) �@ �Q�D�������������グ��w�͋`�� �@���ʏ������O�Z����(���S�T���Ԉȏ�̎c��)���������ۂɁA�S�T���Ԃ��z���鎞�ԊO�J���̊������������߂邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B�܂����̊������͂Q�T�����闦�Ƃ��邱�Ƃ��w�͋`���Ƃ���܂����B �@ �R�D�N���L���x�ɂ����ԒP�ʂŎ擾�\ �@�J�g����̒����ɂ��P�N�ɂT���������x�Ƃ��Ď��ԒP�ʂŎ擾���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B�������A�J���҂����P�ʂ̎擾����]�����ꍇ�́A�g�p�҂����ԒP�ʂɕύX�͏o���܂���B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���ی��z�N�x�X�V�̐\���E�[�t�����ύX�ɂ��� �@�����Q�P�N�x����J���ی��̔N�x�X�V�i�ی����̊T�Z�E�m��\��)���ύX�ƂȂ�܂��B �Ȃ��A�J���ی��̕ی����̌v�Z�͍��܂łǂ���O�N�x(�S���P������R���R�P���܂ł̂P�N��)�Ɏx����ꂽ���^�����ƂɌv�Z���܂��B �@ �@�@�y�\�������z�@�U�^�P�`�V�^�P�O�@�i�����Q�O�N�x�܂łS�^�P�`�T�^�Q�O�j �@�@�y�[�t�����z�@��P���i�ꊇ�j�G�V�^�P�O�@��Q���G�P�O�^�R�P�@��R���G���N�P�^�R�P �@ �N�x�X�V�̐\�����͂T�����`�U����ɑ��t�����\��ł��B�\�������ύX�ɂ��Љ�ی��̎Z���b�Ɠ������ɂȂ�܂��̂ŁA���߂̏��������肢���܂��B�J���ی��̕ی����̎Z��̍ۂɂ͋��^�䒠�E���^�x�������Ȃǂ̏������K�v�ƂȂ�܂��B �@ �J���ی��̔N�x�X�V�葱�ɂ��Ă͓��������ł��戵���Ă���܂��B ���˗��̏ꍇ�͂����߂ɂ����k���������B �@ ���J�Еی������E�ٗp�ی��������ύX�ƂȂ�܂��B �@�{�N�x�ی������̉��肪�\�肳��Ă��܂����A���ݐR�c���ł��B���܂莟�您�m�点�������܂��B�N�x�X�V�\�����̑��t�̍ۂɂ��ē������\��ł��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z���{�Ǐ����N�ی��������ۂɕς��܂� �@�����Q�O�N�P�O���P�����Љ�ی����ň����Ă������{�Ǐ����N�ی��̋Ɩ����w�����ہx�ɕς��܂��B�ύX�̊T�v�͈ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B �@ �@�����N�ی��̎葱�Ɩ��̐\���������ꕔ�ύX�ƂȂ�܂��B �@�@���N�ی��̔��s�A���N�ی��̋��t�A�C�ӌp����ی��҂̎葱�Ȃ� �@�@�������A���ʂ͋����ۂ̑������e�Љ�ی��������ɐݒu����܂��̂ŁA�]���ǂ���Љ� �@�@�ی��������Ő\���E�͏o���o���܂��B �@���Љ�ی��̓K�p�Ɋւ���葱�͏]���ǂ���Љ�ی��������ł����Ȃ��܂��B �@�@�Љ�ی��̐V�K�K�p�A��ی��Ҏ��i�擾�E�r���A�Z���b�́A���z�ύX�͂Ȃ� �@�����݂̌��N�ی��͈��������g�p�ł��܂��B �@�@���N�ی��̕ی��҂��ς�邱�Ƃɂ��ی����ς��܂��B�����������\�肳��Ă��܂����A �@�@����܂ł̊Ԃ͍��܂ł̕ی����g���܂��B �@���[�����m���͎Љ�ی��������Ŕ��s���܂��B �@�@���N�ی��E�����N���ی����[�����m���͏]���ǂ���Љ�ی����������甭������܂��B �@�����ʌ��N�ی����̕ύX�͂���܂���B �@�@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz������Ǘ��E�ł͂���܂���? �@�J����@�ɂ��w�Ǘ��ēҁx�ɂ��Ă͘J�����ԁE�x�e�E�x���̓K�p���珜�O����Ă���A�c�Ǝ蓖��x���蓖�Ȃǂ̊��������̎x�����͕s�v�ƂȂ�܂��B �����Ō����w�Ǘ��ēҁx�͉�Ђ̊Ǘ��E�Ɠ���ł͂���܂���B��Ђ̊Ǘ��E�ɂ͈ꗥ�Ɏc�Ƒ���x����Ȃ����Ƃɂ��Ă���Ǝc�Ƒ㖢�����̎w�E�������鋰�ꂪ����܂��B �@����A�����J���Ȃ��w�Ǘ��ēҁx�̓K�����ɂ��ĒʒB���o����܂����B ����̓��e�͑��X�ܓW�J���鏬���ƁE���H�X�ƂƂ���Ă��܂����A��{�I�ȕ����͈�ʂ̊�Ƃ̔��f�������ł��B������Ǘ��E�ɂȂ��Ă��Ȃ����Ċm�F���Ă��������B �@ �Ǘ��ē҂Ƃ́E�E�E �@�Ǘ��ē҂͈�ʓI�ɁA�J�������̌���ȂǘJ���Ǘ��ɂ��Čo�c�҂ƈ�̓I�ȗ���ɂ���� �@�������B�i��Ƃ��C������E����̖�t�҂̑S�Ă��Ǘ��ē҂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�j �@�܂��A�J�����ԁE�x�e�E�x�����̋K�������Ɋ������邱�Ƃ��K�v�Ƃ����d�v�ȐE���Ɛ� �@�C�������̂Ɍ���Ǘ��ē҂Ƃ���B ��̓I�Ȕ��f��i�����Q�O�N�X���ʒB�̗v��j �@ �Ǘ��ē҂ƂȂ�Ȃ��d�v�ȗv�f �@�q�E�����e�A�ӔC�ƌ����r �@�@���]�ƈ��̗̍p�ɂ��ĐӔC�ƌ������Ȃ��B �@�@���]�ƈ��̉��قɂ��ĐE�����e�Ɋ܂܂ꂸ�A�����I�Ɋ֗^���Ă��Ȃ��B �@�@�������̐l���l�ۂɂ��ĐE�����e�Ɋ܂܂ꂸ�A�����I�Ɋ֗^���Ă��Ȃ��B �@�@���Ζ����A���莞�ԊO�J���̖��߂ɂ��ĐӔC�ƌ������Ȃ��B �@�q�Ζ��l�ԁr �@�@���x���A���ޓ��ɂ�茸���̐��فA�l���l�ۂł̕��̕]���ȂǕs���v�Ȉ����������B �@�q�������̑ҋ��r �@�����ԒP���Ɋ��Z�����ꍇ�Ɉ�ʏ]�ƈ��̒����z�ɖ����Ȃ��B �@ �Ǘ��ē҂ƂȂ�Ȃ��Ɣ��f�����⋭�v�f �@�q�Ζ��l�ԁr �@�@�������ԘJ����]�V�Ȃ������ȂǁA���ۂɂ͘J�����ԂɊւ���ٗʂ��قƂ�ǂȂ��B �@�@���J�����Ԃ̋K�����镔���Ɠ��l�̋Ζ��l�Ԃ��J�����Ԃ̑唼�����߂�B �@�q�������̑ҋ��r �@�@����E�蓖���̗D���[�u�������������x�����Ȃ����Ƃ��l������Ə\���ł͂Ȃ��B �@�@���N�Ԃ̒������z����ʏ]�ƈ��Ɣ�ד����x�ȉ��ł���B �@ �@�c�Ƒ�̖������Ȃǂ̍ٔ��ɔ��W�����ꍇ�́A�Ǘ��ē҂̉��߂͋����Ƃ炦���Ă���A�قƂ�ǂ̏ꍇ�ɉ�Б��Ɏx�������߂��o����Ă���悤�ł��B�����E�H�꒷�Ȃǂ̖�E�ł��c�Ƒ�̎x�������K�v�ƂȂ�P�[�X�͑����ł��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����N���ی��̕ی��������肳��܂��� �@�����Q�O�N�X����(�P�O���[�t��)�������N���̕ی������O�D�R�T�S�������グ���܂����B ����ی����̌v�Z������ꍇ�ɂ͒��ӂ����ĉ������B �@��ʔ�ی��҂̏ꍇ�E�E�E �@�@�����Q�O�N�W���܂ŁG�P�O�O�O���̂P�S�X�D�X�U�@�A�@�X������G�P�O�O�O���̂P�T�R�D�T�O ���@�����ɂ������N���ی��̕ی������͕����Q�X�N�܂Ŗ��N���肳��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڂ����͎Љ�ی����g�o�@http://www.sia.go.jp�@�ł��m�F���������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Œ���������肳��܂� �@�����Q�O�N�P�O���Q�T����茧�̍Œ���������Ԋz�V�U�U�~�i�R�O�~�t�o�j�ɉ��肳��܂��B �����̏�p�E�Վ��E�p�[�g�E�A���o�C�g���S�Ă̘J���҂ɓK�p����A���̋��z�ȏ�̒������x�����K�v������܂��B���^�v�Z�Ȃǂ̍ۂ͏[�����ӂ��Ă��������B ���Œ�����̓K�p���O�K�肪�p�~����A���z����ƂȂ��Ă��܂��B �Œ�����̌��z�������Ȃ��ׂɂ͎��O�Ɍ��z���ዖ�̐\�����K�v�ł��B ���z�̑Ώۂ͇@���_���͐g�̂̏�Q�ɂ�蒘�����J���\�͂��Ⴂ�҂ƁA�A�f���I�J���ɏ]������ �҂Ƃ���Ă���A���z�̗��R�����m�ɂȂ��Ă���K�v������܂��B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�����Q�O�N�Z���b�͂̒�o�ɂ��� �@�Љ�ی��̕�V���z�Z���b�͂̒�o�������߂Â��Ă��܂����B �Ώۂ́A���N�V���P�����݂̎Љ�ی���ی��ґS���ƂȂ�܂��B(�U�����i�擾�҂�����) �Љ�ی����������X������鎑�����Q�l�ɂ��đ��߂ɍ쐬���܂��傤�B ��o���Ԃ͂V�^�P�`�V�^�P�O�ƂȂ�܂��̂ŖY�ꂸ�ɒ�o���Ă��������B �@�@���ڍׂ͂�������������������@�w�莞����i�Z���b��)�x �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�ܗ^�x���͂̒�o�ɂ��� �@�ܗ^���x�������Ƃ��͂T���ȓ��ɏܗ^�x���͂��Љ�ی��������Ȃǂɒ�o����K�v������܂��B �ܗ^�̎x�������I�������A�����Ɏx���͂̍쐬�E��o������悤�ɂ��܂��傤�B ���łɏܗ^�x�����I����Ă��鎖�Ə��͎x���͂̒�o��Y��Ă��Ȃ����m�F���Ă��������B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڍׂ͂�������������������@�w�ܗ^�x�����x �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz�Œ�����@���ς��܂� �@�Œ�����@����������A�V���P�����{�s����܂��B �@��ȉ����_�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B �@�@���n��ʍŒ�����̕s�����̏ꍇ�̔����z�̏�����Q���~����T�O���~�ɂȂ�܂��B �@�@���Œ�����̓K�p���O�K�肪�p�~����A���z����ƂȂ�܂��B �@�@���h���J���҂ɂ͔h����̒n��ʍŒ�������K�p�ƂȂ�܂��B �@�@���Œ�����z�̕\���͎��Ԋz�݂̂̕\���Ɉ�{������܂��B �ڍׂ̓��[�t���b�g�Ȃǂł��m�F�������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���ی��z�N�x�X�V�ɂ��� �@�J���ی��̔N�x�X�V�葱(�ی����̊T�Z�E�m��\������є[�t)�͂S���P������T���Q�O���܂łƂȂ�܂��B���łɎ��Ǝҗl���Ăɐ\�����ꎮ���X������Ă���Ǝv���܂��̂ŁA���߂̎葱�����肢���܂��B �J���ی��̕ی����͑O�N�x(�S���P������R���R�P���܂ł̂P�N��)�Ɏx����ꂽ���^�����ƂɌv�Z����܂��B�ی����̎Z��̍ۂɂ͋��^�䒠�E���^�x�������Ȃǂ̏������K�v�ƂȂ�܂��B �J���ی��̔N�x�X�V�葱�ɂ��Ă͓��������ł��戵���Ă���܂��̂ŁA���˗��̏ꍇ�͂����߂ɂ����k���������B �@ ����������Ă���w�ҕt����E�x�����c���x�ɂ��� �@���N�x�̐\�����ɏ�L�̏��ނ���������Ă��܂��B�J���ی��̊m��\���̍ۂɏ[���z�����������N��̊T�Z�ی����ɏ[�����Ă��]��ꍇ�Ɏg�p���܂��B��ʋ��o���ւ̏[���y�ъҕt�̐��������̗p���ōs�Ȃ��܂��B �@ �����N�x�̔N�x�X�V�����ɂ��� �@�����Q�P�N�x�̘J���ی��̔N�x�X�V�����͂Q�����قǒx���Ȃ�܂��B �@�@�@�@�@�@�@�������Q�P�N�U���P���`�V���P�O���@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�ڍ��߰�ނցl�J���ی��̔N�x�X�V �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���Ǘ��z�p�[�g�^�C���J���@����������܂��� �@�p�[�g�^�C���J���@�̉����ɂ��ٓ����̘J�������̖���(���ʓ��̌�t)�������lj�����܂����B �ٓ��ꎞ�̏��ʌ�t(�J�������ʒm)�Ȃǂ̍ۂɂ͒��ӂ��K�v�ł��B �ᔽ�̏ꍇ�͂P�O���~�ȉ��̉ߗ��ɏ������܂��B�i�����Q�O�N�S���P���{�s�j �@ �@�@�����ɂ�����J�������̖����E�E�E��������ŏ��ʂȂǂ̌�t���K�v�ɂȂ�܂����B �@�@�P�D�����Ɋւ��鎖�� �@�@�Q�D�ސE�蓖�Ɋւ��鎖�� �@�@�R�D�ܗ^�Ɋւ��鎖�� �@ �@�J����@�ɂ��J�������̖����E�E�E��������ɂ��ύX�Ȃ�(�]�O�ǂ���) �@�@�y���ʂɂ���t���K�v�Ȏ����z �@�@�P�D�J���_��̊��ԁA�Q�D�A�Ƃ̏ꏊ�A�]�����ׂ��Ɩ��A�R�D�J�����ԂɊւ��鎖�� �@�@�S�D�����Ɋւ��鎖���A�T�D�ސE�Ɋւ��鎖���i���ق̎��R���܂ށj �@�@�y�������K�v�Ȏ����z�E�E�E�ʏ�͏A�ƋK���̊J�����ɂ�薾�� �@�@�U�D�ސE�蓖�Ɋւ��鎖���A�V�D�����Ɋւ��鎖��(��L�ȊO) �@�@�W�D�J���҂̕��S����H��A��Ɨp�i���̑��A�X�D���S�y�щq���Ɋւ��鎖�� �@�@�P�O�D�E�ƌP���Ɋւ��鎖���A�P�P�D�ЊQ�⏞�y�ыƖ��O�̏��a�}���Ɋւ��鎖�� �@�@�P�Q�D�\���y�ѐ��قɊւ��鎖���A�P�R�D�x�E�Ɋւ��鎖�� �@ ����̉����ɂ��p�[�g�^�C���J���҂ɑ��l�X�ȋ`���E�w�͋`�����K�肳��܂����B�ڍׂ͌����J���Ȃg�o��p���t���b�g�Ȃǂł��m�F���������B �@�w��L�ȊO�̎�ȍ��ځx �@�@�ҋ�����ɂ�����l�����������̐����`���i���������߂�ꂽ�Ƃ��j �@�@�ʏ�̘J���҂֓]������[�u�̋`�� �@�@�E�����s�ɕK�v�ȋ���P���̎��{�`�� �@�@���������{�݂̗��p�@��̔z���`�� �@�@�ҋ��̍��ʓI��舵���̋֎~�@�Ȃ� �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�������҈�Ð��x���͂��܂�܂� �@�����Q�O�N�S�����������҈�Ð��x���͂��܂�܂��B ��ی��ҁE��}�{�҂ň��̏����ɊY��������́A�������҈�Ð��x�ɉ������邱�ƂɂȂ�܂��B ���̏ꍇ�A���݉����̐��{�Ǐ����N�ی��̔�ی��ҁE��}�{�҂ł͂Ȃ��Ȃ�܂��B �@ �q�����̏����r �@�@���V�T�Έȏ�̕��@���U�T�`�V�S�̕��ň��̏�Q�̂���� �@ �q�K�v�Ȏ葱���r �@��ی��ҁE��}�{�҂��V�T�ɓ��B�����ꍇ�Ȃnj������҈�Ð��x�ֈڍs�������ɂ��ẮA �Љ�ی���������������v�����g��������i�r���ͣ�܂��͢��}�{�҈ٓ��ͣ���X������܂��B �K�v�������L�����Ĕ�ی��ҏ�Y�t���ĕԑ����Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z���ی��������ύX����܂� �@�����Q�O�N�R����(�S���[�t������)��萭�{�Ǐ����N�ی��̉��ی��������ύX����܂��B ����ی����̌v�Z������ꍇ�ɂ͒��ӂ����ĉ������B �@�����Q�O�N�R���ȍ~�G�P�D�P�R���i���݂P�D�Q�R���j �@ ���^�T���͗��������̏ꍇ�͂S�����̋��^����ύX�ƂȂ�܂��B �Ȃ��A�����N���ی��̕ی������ɂ͕ύX������܂���B �����N�ی��g���ɉ�������Ă�����̕ی������͑g���ɂ���ĈقȂ�܂��̂Ŋm�F���Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����N���ی��̕ی��������肳��܂��� �@�����P�X�N�X����(�P�O���[�t��)�������N���̕ی������O�D�R�T�S�������グ���܂����B ����ی����̌v�Z������ꍇ�ɂ͒��ӂ����ĉ������B �@��ʔ�ی��҂̏ꍇ�E�E�E �@�����P�X�N�W���܂ŁG�P�O�O�O���̂P�S�U�D�S�Q�@�A�@�X������G�P�O�O�O���̂P�S�X�D�X�U ���@�����ɂ������N���ی��̕ی������͕����Q�X�N�܂Ŗ��N���肳��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Œ���������肳��܂��� �@�����P�X�N�P�O���P�X����茧�̍Œ���������Ԋz�V�R�U�~�i�P�X�~�t�o�j�ɉ��肳��܂����B �����̏�p�E�Վ��E�p�[�g�E�A���o�C�g���S�Ă̘J���҂ɓK�p����A���̋��z�ȏ�̒������x�����K�v������܂��B���^�v�Z�Ȃǂ̍ۂ͏[�����ӂ��Ă��������B �@�Y�ƕʂ̍Œ�����͕����P�W�N�P�Q���ɉ��肳��Ă��܂��̂ŁA�Ώۂ̕��͒��ӂ��Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz��W�E�̗p���̔N������ł��Ȃ��Ȃ�܂� �@�ٗp���@�̉����ɂ��A�����P�X�N�P�O���P������J���҂̕�W�y�э̗p���̔N������֎~����܂��B �J���҂̕�W�y�э̗p�̍ۂɂ͌����Ƃ��ĔN��s��Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B����͌����E�ƈ��菊�ł̋��l�����łȂ��A��ʂ̋��l�L���Ȃǂ��Y�����܂��B���l�̓��e�Ȃǂɂ��Ă͌����E�ƈ��菊���玑���̒�o����������߂��邱�Ƃ�����܂��B �@ �@��O�I�Ɉȉ��ɂ��Ă͔N������F�߂���ꍇ������܂��B �@�@����N�̔N�������Ƃ���ꍇ�i���Ԃ��߂��ٗp�͕s��) �@�@���J����@�Ȃǖ@�߂ɂ��N���������Ă���Ɩ��̏ꍇ �@�@�������Α��ɂ��L�����A�`����}��ړI�Ŏ�N�ғ����ٗp����ꍇ �@�@�@�i�E�ƌo���͕s��Ƃ��邱�ƁB���Ԃ��߂��ٗp�͕s�B�V�K�w���҂Ɠ����̏����ł��邱��) �@�@���Z�\���̌p���̖ړI�ŎГ��Ŕ��ɏ��Ȃ��N��w���U���邽�߂Ɍٗp����ꍇ �@�@�Ȃ� �@�N�����݂���ꍇ�͂��̗��R�����ʂȂǂɂ����邱�Ƃ��K�v�ł��B �@ ����O�K��ɂ��Ă͏ڍ�茈�߂�����܂��̂Ń��[�t���b�g�܂��͊NJ��̌����E�ƈ��菊�ł��m�F���������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz�O���l���ٗp���鎖�Ǝ҂͓͏o���K�v�ƂȂ�܂� �@�����ٗp���@�̐����ɂ��A�O���l���ٗp����ꍇ�̃��[�����V�����Ȃ�܂��B �@��ȓ��e�G�O���l�ٗp�̓͏o(�`��)�A�O���l�J���҂̌ٗp�Ǘ��̉��P��(�w�͋`��) �O���l�̌ٗp�̓͏o���`��������܂��̂ŁA���݊O���l���ٗp���Ă���ꍇ�͖Y�ꂸ�ɓ͏o�������Ȃ��ĉ������B�����P�X�N�P�O���P������{�s�ƂȂ�܂��B �y�O���l�ٗp�̓͏o�ɂ��āz �@�O���l�J���҂��ٗp����ꍇ�A�����E�ݗ����i�Ȃǃn���[���[�N�ւ̓͏o���K�v�ƂȂ�܂��B �@���łɌق�����Ă���ꍇ���ΏۂƂȂ�܂��̂ŁA�Y�ꂸ�Ɏ葱�������Ȃ��ĉ������B �@�@�i�P�j�ٗp�ی��̔�ی��҂ł���O���l�̓͏o �@�@�@�ٗp�ی��̎��i�擾�͖��͑r���͂̔��l���ɁA�ݗ����i�A�ݗ������A���Г����L�ڂ��� �@�@�@�͂��o�邱�Ƃ��ł��܂��B�͏o�����͎擾�͖��͑r���͂̒�o�����Ɠ��l�ł��B �@�@�i�Q�j�ٗp�ی��̔�ی��҂ł͂Ȃ��O���l�̓͏o �@�@�@�͏o�l��(��R���l��)�ɁA�����A�ݗ����i�A�ݗ������A���N�����A���ʁA���Г����L�� �@�@�@���ē͂��o�Ă��������B �͏o�����͌ٓ���A���E�̏ꍇ�Ƃ��ɗ��������܂łł��B �@�@�i�R�j�����P�X�N�P�O���P�����_�Ō��Ɍق�����Ă���O���l�̓͏o �@�@�@�͏o�l��(��R���l��)�ɁA�����A�ݗ����i�A�ݗ������A���N�����A���ʁA���Г����L�� �@�@�@���ē͂��o�Ă��������B �͏o�����͕����Q�O�N�P�O���P���܂łł��B �@�@�@�i�������A���̊Ԃɗ��E�����ꍇ�́A�i�P�j���́i�Q�j�ɏ]���͏o�j �@ �ڍׂ̓n���[���[�N���̃��[�t���b�g���������������B�����J���Ȃ̂g�o�ł��m�F�ł��܂��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�ٗp�ی��z�ٗp�ی��̎��i�v���Ȃǂ��ς��܂� �@�ٗp�ی��@���ς��A���i�v���Ȃǂ��ύX�ƂȂ�܂��B �ύX�ƂȂ���e�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B�W����]�ƈ��̕�������ꍇ�͂����ӂ��������B �@ �P�D�ٗp�ی��̎��i�v���̕ύX �@�ٗp�ی��̊�{�蓖�����邽�߂ɂ͂P�Q���ȏ�̔�ی��Ҋ��Ԃ��K�v�ƂȂ�܂��B �@�����Ƃ��ĕ����P�X�N�P�O���P���ȍ~�ɗ��E���ꂽ�����ΏۂƂȂ�܂��B �@�@(��)�@��ʔ�ی��ҁ@�E�E�E�U���ȏ�(�e���P�S���ȏ�) �@�@�@�@�@�Z���Ԕ�ی��ҁE�E�E�P�Q���ȏ�(�e���P�P���ȏ�) �@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@(�V)�@�S�Ă̔�ی��ҁE�E�E�P�Q���ȏ�(�e���P�P���ȏ�) �@ �Q�D�玙�x�Ƌx�ɂ̋��t���̕ύX �@���t�����x�ƑO�����̂S�O������T�O���Ɉ����グ���܂��B �@�����P�X�N�S���P���ȍ~�ɐE�ꕜ�A���ꂽ������A�����Q�Q�N�R���R�P���܂łɈ玙�x�Ƃ��J�n �@���ꂽ���܂ł��ΏۂƂȂ�܂��B �@ �R�D����P�����t�̗v���E���e�̕ύX �@����P�����t�̏���̎v������ی��Ҋ��ԂR�N�ȏォ��P�N�ȏ�Ɋɘa����܂��B �@�܂��A���t���E����z�Ȃǂ���{������܂��B �@�����P�X�N�P�O���P���ȍ~�Ɏw��u���̎�u���J�n���ꂽ�����ΏۂƂȂ�܂��B �@�@(��)�@��ی��Ҋ��ԂR�N�ȏ�T�N�����E�E�E�Q�O��(����P�O���~) �@�@�@�@�@��ی��Ҋ��ԂT�N�ȏ�@�E�E�E�S�O��(����Q�O���~) �@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@(�V)�@��ی��Ҋ��ԂR�N�ȏ�@�E�E�E�Q�O��(����P�O���~) �@�@�@�@�@����Ɍ����ی��Ҋ��ԂP�N�ȏ�Ŏ\ �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�ٗp�ی��z�ٗp�ی����������肳��܂��� �@�ٗp�ی������P�O�O�O���̂S�D�T�����������邱�Ƃ��S�����Ɍ��肵�܂����B �V�����ٗp�ی����͕����P�X�N�S���̒������ؓ��̋��^����ύX�ƂȂ�܂��B �@�S�����ؓ��̋��^������O�̕ی������Ōv�Z���Ă���ꍇ�́A�T�����ؓ��ȍ~�̋��^����ٗp�ی�������ύX���A�S�����̌y�����E���ċ��^����T�����邱�Ƃ��K�v�ł��B ������̌ٗp�ی������̉���̒x��͍���ł̐R�c�E����x��ɂ����̂ł��B �@ ����19�N4������̌ٗp�ی�����
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�Z���ꗗ�\�ŏ]�ƈ��̏Z���̊m�F���E�E�E �@�Љ�ی����ł͔�ی��҂Ƃ��̔�}�{�z��҂̏Z���ꗗ�\�̒����Ă��܂��B �]�ƈ��̕��̏Z�����ς�����ꍇ�͏Z���ύX�̓͏o���K�v�ƂȂ�܂����A���ݎЉ�ی����ɓo�^����Ă���Z�����킩��Ȃ��ƌ���̊m�F���o���܂���B���̋@��ɓo�^����Ă���Z�����m�F���邱�Ƃ��������߂��܂��B �@����Љ�ی����Œ���ꗗ�\�͏]�ƈ�(��ی���)�Ƃ��̔�}�{�z��҂̕��̏Z���ƂȂ�܂��B �Z���ꗗ�\�̒��邽�߂ɂ́A����̗l���ŊNJ��̎Љ�ی��������ɐ\�����K�v�ł��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���ی��z�N�x�X�V�ɂ��� �@�J���ی��̔N�x�X�V�葱(�ی����̊T�Z�E�m��\��)�͂S���P������T���Q�O��(�����͗���)�܂łƂȂ�܂��B�ʏ�S���P���ɐ\�����ꎮ���X������܂����A���N�͌ٗp�ی����̐R�c���s���Ă��邽�ߑ��t���x��Ă���悤�ł��B �J���ی��̕ی����͑O�N�x(�S���P������R���R�P���܂ł̂P�N��)�Ɏx����ꂽ���^�����ƂɌv�Z����܂��B�ی����̎Z��̍ۂɂ͋��^�䒠�E���^�x�������Ȃǂ̏������K�v�ƂȂ�܂��B �J���ی��̔N�x�X�V�葱�ɂ��Ă͓��������ł��戵���Ă���܂��̂ŁA���˗��̏ꍇ�͂����߂ɂ����k���������B�i���ݐ_�ސ쌧���̎��Ǝҗl�̂ݎ葱�������Ă��܂�) �@ �N�x�X�V������Əo����t�͗\��ʂ�s����悤�ł��B �_�ސ�J���ǂ̂g�ohttp://www.kana-rou.go.jp/�Ŋm�F���������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�ڍ��߰�ނցl�J���ی��̔N�x�X�V �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���Ǘ��z���N�̎O�Z����͂̏����͏o���Ă��܂���? �@�c�ƁE�x���o�ɂ͎O�Z���肪�K�v�ł��B �O�Z����ɂ͊��Ԃ�����A�ʏ�͂P�N�ƂȂ��Ă��܂��̂Ŗ��N�͏o���s�����ƂɂȂ�܂��B ����̊��Ԃ��S������Ƃ��Ă�����������悤�ł��B�܂��͑O��̓͏o�����m�F���Ă��������B �L�������ȍ~�̋��Ԃ͎c�Ƃ�x���J���͏o���Ȃ��Ȃ�܂��B �@ �@�O�Z����i���ԊO�J���E�x���J������)�Ƃ́E�E�E �@�@�@�Ɩ��ʂ̑����ȂǂŎc�Ƃ�x���o���K�v�ȂƂ���A�Z���������̏o�Γ����𑝂₷�ꍇ�́A �@�@���炩���ߘJ���҂̑�\�Ƌ��肵�A�J����ē��ɓ͏o���s���K�v������܂��B �@�@���������̎x���������Ă��Ă��͏o�������Ɏc�Ƃ�x���o���s�����Ƃ͈�@�ƂȂ�܂��B �@�@�Ǝ��K�͂ɊW�Ȃ��A�c�Ƃ�x���J�����s�����Ə��͓͏o���K�v�ŁA�e���Ə��P�ʂɓ͏o�� �@�@�s���܂��B�i�x�X�A�c�Ə��Ȃǁj �@ �@�w���ԊO�J����x���J�����s�킹��Ƃ��ɕK�v�ƂȂ�葱�x �@�@�@�P�D���炩���ߘJ���҂̑�\(��)�Ɖ������鎞�ԂȂǂɂ��ċ�������܂��B �@�@�@�Q�D����ɂ��ƂÂ��͏o�����쐬���NJ��̘J����ē��ɓ͏o���s���܂��B �@�@�@�R�D���ۂɘJ�������c�Ƃ�x���o�ɂ��Ċ����������x�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�ڍ��߰�ނցl�O�Z����E�ό`�J�����Ԑ� �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���Ǘ��z�ό`�J�����Ԑ��̓����͕K�v����܂���? �@�ό`�J�����Ԑ��́A�c�Ǝ��ԁi���ɋx���o�j�̍팸�̂��߂ɗL���Ȏ�i�ł��B �P���W���ԁA�P�T�S�O���ԂƂ�����̋Ζ��̐��ɂ��Ă��܂��ƁA�x���o��c�Ǝ��Ԃ̑����ƂȂ��Ă��܂��ꍇ������܂��B�ό`�J�����Ԑ��ɂ�肤�܂��Ή��ł��邱�Ƃ�����܂��B �����Ԃς��ĂP�T�ԂS�O���Ԃɂ���悭�A�P���W���Ԉȓ��ɂ���K�v�͂���܂���B �@ �@��������ꍇ�́A�J���҂̑�\�Ƌ��肵�A�J����ē��ɓ͏o���s���K�v������܂��B ����E�͏o���s��Ȃ��ꍇ�́A�P���W���ԁE�P�T�ԂS�O���Ԃ��z�������Ԃ͊�ǂ���Ɏc�ƁE�x���o�ƂȂ�܂��B�O�Z����̒�o�����ɂ��킹�ē����̌������������߂��܂��B �@ �ȉ��̂悤�ȏꍇ�͕ό`�J�����Ԑ��ɊY�����܂��B �@���N�ԃJ�����_�[�ȂǂŏT�T������Ζ������߂��ꍇ(�T�S�O���Ԉȏ�) �@���P���̘J�����Ԃ��W���Ԃ��z���邱�Ƃ̂����Ζ����߂��ꍇ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�ڍ��߰�ނցl�O�Z����E�ό`�J�����Ԑ� �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���E�Љ�ی��z�Љ�ی��ƘJ���ی��̓͏o�������ɍs���܂� �@�Љ�ی��E�J���ی����������Z���^�[�ŎЉ�ی��ƘJ���ی��̓͏o�������ɍs����悤�ɂȂ�܂����B��L�Z���^�[�͎Љ�ی����������ɐݒu����Ă��܂��B �����Ɏ�t���ł���͏o�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B �@�@���Ə��̐ݒu�@�A���Ə��̏Z���▼�̂̕ύX�@�B�ی��葱�㗝�l�̑I�C�E��C �@�C�]�ƈ��̗̍p�@�D�]�ƈ��̎����ύX�@�E�]�ƈ��̑ސE(���E�[��t���s�v�̏ꍇ�̂�) �@�F���Ə��̔p�~�E�x�� �Z���^�[�ł͓͏o�̎�t�݂̂��s���܂��B���e�R���͊e�@�ւɉ��čs�����߁A���������܂ł̎��Ԃ͒ʏ��肩����Ǝv���܂��B ���A�����͏o���ł��鎖�Ǝ҂͎Љ�ی��ƘJ���ی��̗����̓K�p�̂�����݂̂ł��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z���i�擾�͎��̔N���蒠�Y�t�ɂ��� �@�Љ�ی��̎��i�擾�͂̍ۂɔN���蒠��Y�t���Ă��܂������A�����P�W�N�P�O���P������Y�t���s�v�ƂȂ�܂��B�������A���Ǝ哙���͏o���̊�b�N���ԍ��⎁���Ȃǂ��������L������Ă��邩�N���蒠�Əƍ��E�m�F���邱�Ƃ��K�v�ł��B �@�w�N���蒠�̓Y�t���s�v�ƂȂ�͏o�x �@�@��ی��Ҏ��i�擾�́A��ی��Ҏ����ύX�́A��R����ی��Ҏ��i�擾�E��ʕύX�E�Z���ύX�� �@�@����ی��҂̎����ύX�̍ۂɂ͎��Ǝ哙�ŔN���蒠�ɕύX��̎������L�����Ē����܂��B �@�@����R����ی��҂̎����ύX�ɏꍇ�͏]���ǂ���N���蒠�̓Y�t���K�v�ł��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����N���ی��̕ی��������肳��܂��� �@�����P�W�N�X����(�P�O���[�t��)�������N���̕ی������O�D�R�T�S�������グ���܂����B ����ی����̌v�Z������ꍇ�ɂ͒��ӂ����ĉ������B �@��ʔ�ی��҂̏ꍇ�E�E�E �@�@�����P�W�N�W���܂ŁG�P�O�O�O���̂P�S�Q�D�W�W�@�A�@�X������G�P�O�O�O���̂P�S�U�D�S�Q �@���@�����ɂ������N���ی��̕ی������͕����Q�Q�N�܂Ŗ��N���肳��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Œ���������肳��܂��� �@�����P�W�N�P�O���P����茧�̍Œ���������Ԋz�V�P�V�~�i�T�~�t�o�j�ɉ��肳��܂����B �����̏�p�E�Վ��E�p�[�g�E�A���o�C�g���S�Ă̘J���҂ɓK�p����A���̋��z�ȏ�̒������x�����K�v������܂��B���^�v�Z�Ȃǂ̍ۂ͏[�����ӂ��Ă��������B �@�Y�ƕʂ̍Œ�����͕����P�V�N�P�Q���ɉ��肳��Ă��܂��̂ŁA�Ώۂ̕��͒��ӂ��Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz�U�������ɂ��� �@���������V�����ʂɂ����đ�萻���Ƃ̋U���������b��ɂȂ��Ă��܂��B ���N�O�܂Ő����Ƃɂ͘J���Ҕh�����F�߂��Ă��܂���ł������A�@�����ɂ��J���Ҕh�����o����悤�ɂȂ�܂����B������A�s�����ɂ����Đ����E�h���̎��Ԓ����Ɛ����w�����{�i�I�ɍs����悤�ɂȂ�܂����B �_���͐����ƂȂ��Ă��Ă��A���Ԃ��h���ƂɊY������Δh���Ƃ̋��E�͏o���K�v�ł��B �@ �@�h���Ɛ����͋敪��������̂ł����A�|�C���g�́w�w�����߂�N�����邩�x�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�Ɩ����s���Ă��錻��ŁA�����̒S���҂��J���҂ɑ��Ďw�����o���ꍇ�͔h���ɊY�����܂��B�H��̃��C����Ƃ͐����͈̔͂ōs�����Ƃ͒ʏ�l�����܂���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڍׂ͂�������������������@�w�h���ƂƐ����Ƃ̈Ⴂ�x �@����̋U�������̎��Ԃ���A����͒����̐����Ƃ⑼�̋Ǝ�̘J���Ҕh���̒������s����Ǝv���܂��B�h���ɊY������Ɩ��������������ȏꍇ�́A���O�ɘJ���Ҕh���Ƃ̎葱���������邱�Ƃ��������߂��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڍׂ͂�������������������@�w�J���Ҕh������)�x �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�����P�W�N�Z���b�͂̒�o�ɂ��� �@�Љ�ی��̕�V���z�Z���b�͂̒�o�����ƂȂ�܂����B �Ώۂ́A�����P�W�N�V���P�����݂̎Љ�ی���ی��ґS���ƂȂ�܂��B(�U�����i�擾�҂�����) ���łɎЉ�ی����������X������Ă��鎑�����Q�l�ɂ��Ă��������B ��o�����͗X���̏ꍇ�͂V�^�P�O�ƂȂ�܂��̂ŁA�x��Ȃ��悤�ɏ��ނ��쐬���Ĕ������Ă������������B �Ȃ��A�S�N�̃T�C�N���ŎZ���b�͒�o���̎��Ə��������s���܂��B�����Ώۂ̎��Ə��͎Љ�ی�����������w�肳�ꂽ���@�Œ������Ă��������B�����ΏۊO�̎��Ə��������Ƃ��ĂS�N�̂����ɒ����ΏۂƂȂ�܂��̂ŁA�͏o���̒�o�Y�����t���[�ނ̕s���Ȃǂ������悤�ɍ���x�_�������Ă݂Ă��������B �����ӁG �@�Z���b�̌v�Z������ہA�x����b�������Q�O������P�V���ɕύX�ƂȂ��Ă��܂��B �@�ԈႢ�̂Ȃ��悤�Ɍv�Z���s���Ă��������B�܂��A�V���ȍ~�̌��z�ύX�����l�Ɏx����b�����͂P�V���ƂȂ�܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڍׂ͂�������������������@�w�莞����i�Z���b��)�x �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�ܗ^�x���͂̒�o�ɂ��� �@�ܗ^���x�������Ƃ��͂T���ȓ��ɏܗ^�x���͂��Љ�ی��������Ȃǂɒ�o����K�v������܂��B �ܗ^�̎x�������I�������A�����Ɏx���͂̍쐬�E��o������悤�ɋC�����܂��傤�B ���łɏܗ^�x�����I����Ă��鎖�Ə��ɂ��Ă͎x���͂̒�o��Y��Ă��Ȃ����m�F���Ă݂Ă��������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڍׂ͂�������������������@�w�ܗ^�x���́x |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz���S�Ǘ��҂̑I�C�����C�Ȃǂ��lj�����܂��� ���S�q���@���̉����ɂ�蕽���P�W�N�S��������S�Ǘ��҂̎��i�v�����ύX�ɂȂ�܂����B �J���҂T�O�l�ȏ�̉^���ƁE���ƂȂǂ̎��Ə��ł͈��S�Ǘ��҂̑I�C���K�v�ł��B �@�P�D�ȉ��ɊY������҂������u���S�Ǘ��ґI�C�����C�v���I���������̂ł��邱�ƁB �@�@�@�@�J�����S�R���T���^���g �@�@�@�A�����P�W�N�P�O���P���܂łɈ��S�Ǘ��҂Ƃ��đI�C����Q�N�ȏ�̌o����L����� �@�Q�D���ƌ�ɕK�v�Ƃ��������ɏ]�������o���N�����Z�k����܂����B �@�@�@��w����(���Ȍn��)�G�R�N���Q�N�A���Z����(���Ȍn��)�G�T�N���S�N �@ �Y�ƈ�̋Ɩ��Ɉȉ��̍��ڂ��lj�����܂����B �J���҂T�O�l�ȏ�̑S�Ă̎��Ə��ł͎Y�ƈ�̑I�C���K�v�ł��B �@�E�ʐڎw���̎��{�y�т��̌��ʂɊ�Â��J���҂̌��N��ێ����邽�߂̑[�u�Ɋւ��邱�� �@ ���S�Ǘ��҂�Y�ƈ�ɂ��Ă͓͏o���K�v�ƂȂ��Ă��܂��B�Y���̎��Ə��͖Y�ꂸ�ɓ͏o���s�� �܂��傤�B���S�q���̐��̐����ɂ��Ă͎Љ�ی��J���m�Ȃǂ̐��Ƃɂ��⍇�����������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڍׂ͂�����@���S�q���Ǘ��̐��̐��� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���ی��z�����P�W�N�̔N�x�X�V�葱�ɂ��� �@�J���ی��̔N�x�X�V�̎����ƂȂ�܂����B �����P�V�N�x�̊m��ی����\���ƕ����P�W�N�x�̊T�Z�ی����\�����s���܂��B ���łɘJ���ǂ��\���������X������Ă���Ǝv���܂��̂Ŋm�F���Ă��������B �@�\���E�[�t�͂S���P������T���Q�Q���ƂȂ�܂��̂ŁA�x��Ȃ��悤�ɏ��ލ쐬�����Ĕ[�t���Ă��������B �@ �@�Ȃ��A�����P�W�N�S������J�Еی������̕ύX���s���Ă��܂��̂ŁA�v�Z�̍ۂɂ͏[�����ӂ��Ă��������B �@ �@���ڂ����͂�����ցw�J���ی��̔N�x�X�V�x �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�x����b�����̌������ɂ��� �@�����P�W�N�V�����炱��܂łQ�O���Ƃ���Ă����x����b�������P�V���ɕύX�ɂȂ�܂��B ����ɂ��A���L�̂悤�Ȉ����ɂȂ�܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B �P�D�����P�W�N�x�̒莞����(�Z���b��) �@�@�S���E�T���E�U���̕�V�x���̊�b�ƂȂ��������ɂP�V�������̌�������ꍇ�ɂ͂��̌��� �@�@�����Čv�Z���܂��B �Q�D�����P�W�N�V���ȍ~�̐�������(���z�ύX��) �@�@�Œ�I�����̕ϓ������������ȍ~(�����P�W�N�S���ȍ~)�p�������R�����Ԃ̂�����̌����� �@�@�V�x���̊�b�ƂȂ����������P�V���ȏ�K�v�ƂȂ�܂��B �@�@�U���܂ł̐�������̏ꍇ�͂Q�O���ȏ�̂܂܂ł��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z���ی��������ύX����܂��� �@�����P�W�N�R����(�T���P���[�t��)��萭�{�Ǐ����N�ی��̉��ی��������ύX����܂����B ����ی����̌v�Z������ꍇ�ɂ͒��ӂ����ĉ������B �@�@�����P�W�N�R���ȍ~�G�P�D�Q�R���i���݂P�D�Q�T���j �Ȃ��A�����N���ی��̕ی������ɂ͕ύX������܂���B �����N�ی��g���ɉ�������Ă�����̕ی������͑g���ɂ���ĈقȂ�܂��̂Ŋm�F���Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���ی��z�J�Еی������ύX����܂��� �@�����P�W�N�S���P�����J�Еی������ύX�ɂȂ�܂��B �����P�W�N�x�̊T�Z�ی����͐V�����J�Еی������A�����P�V�N�x�̊m��ی����͍��܂ł̘J�Еی������g�p���邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA�N�x�X�V�̍ۂɂ͏[�����C�������������B �܂��A���܂ł̋Ǝ�敪�ł��̑��̊e�펖�ƂɊY�����Ă������́A�V���ɂS�̋敪�ɕ��ނ���܂��B�N�x�X�V�̐\�����ł͑��̋Ǝ�敪�̕��Ƃ͈قȂ�L�ڕ��@�ƂȂ�܂��B ���Ƃ��c�ޕ��͘J������ύX�ƂȂ������Ƃ̎�ނ�����܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B �ڂ����͑��t�����N�x�X�V�̎��������m�F���������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�@�l�W�z�V��Ж@�ɂ��� �@�V��Ж@�̎{�s�ɂ��A�Œ᎑�{����L����Ђ̔p�~�A�V����������ЂƂ�����Ќ`�Ԃ̒lj��ȂǁA�������N�ɂ͂Ȃ��傫�ȕύX���s���܂��B �@ �w�V��Ж@�̕ύX�_�̊T�v�x �@�ύX�_�͑���ɂ킽��܂����A�����̕��ɊW����Ǝv������e�͈ȉ��̒ʂ�ł��B �@�@������ЂƗL����Ђ��P�̉�Зތ^�i������Ёj�Ƃ��ē��� �@�@�@��Ж@�{�s��͗L����Ђ̐ݗ��͂ł��Ȃ��Ȃ�܂��B �@�@�V���ȉ�Зތ^�i������Ёj�̑n�� �@�@���K�͂Ȋ�����Ђ̋K�����ɘa �@�@�@������̍Œ�l���̊ɘa�A�č����̐ݒu�`����p�~�i�P�l������̊�����Ђ�F�߂�j �@�@�@������A�č����̔C���������\�i�Œ��P�O�N�j �@�@��v�Q�^���x�̑n�� �@�Œ᎑�{���K���̔p�~�A�ގ������K���̔p�~ �@ �w���݂̗L����Ђ́H�x ���݂̗L����Ђ́A����L����ЂƂ��Ă��̂܂ܑ������邩�A������ЂɕύX�����ʂ肪�l�����܂��B �@�L����Ђ̂܂܁E�E�E�@�����͍��̗L����Ђ̂܂܂Ŏ葱���͕K�v����܂���B �@������ЂɕύX�E�E�E�@�����͕K�v����܂��A��Бg�D�̕ύX�葱���K�v�ł��B ���K�͂Ȋ�����Ђł͋K�����ɘa����܂����A���݂̗L����Ђɔ�ׂ�Ƒg�D��葱�ȂǑ����ʓ|�Ȗʂ�����܂��B�ǂ���̑g�D�Ƃ���̂��������Ă������Ƃ��K�v�ł��B �@���V��Ж@�̎{�s�����T���P���Ɍ��肵�܂����B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�V��Ж@�ɂ��āx�E�E�E�@���ݗL����Ђ̕��@�^�@�V�K�ɐݗ������ �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz�����Ƃւ̘J���Ҕh�����Ԃ̉����ɂ��� �@���݁A���̐����ɌW���Ɩ��̔h���\���Ԃ͂P�N�ɐ�������Ă��܂��B�������A�����P�W�N�R���P���ȍ~�ɐV���ɔh�����J�n����ꍇ�́A�ȉ��̎葱���s�����ƂōŒ��R�N�Ԃ̔h�����\�ƂȂ�܂��B �@�@�@�h����J���҂̉ߔ�����\����ӌ�������s���A�h���������Ԃ��߂邱�ƁB �@�@�A�h���悩��h�������Ǝ҂ɑ��Ĕh����������(������G��)�̒ʒm�����邱�ƁB �@�@�B�J���Ҕh���_���������͕ύX���邱�ƁB �@ �Ȃ��A�h���Ƃ̋��E�͏o�̍ۂɐ����Ƃւ̔h�����s���Ɛ\�����Ă��Ȃ����Ǝ҂́A�����Ƃւ̔h�����s�����߂ɕύX�͓��̎葱�����K�v�ƂȂ�܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���葱�͂�����w�J���Ҕh�����Ɛ\���x �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J���ی��z�J�Еی��̖��������Ǝ�ɑ����p�����̋��� �@�J���҂��P�l�ł��ق��Ă��鎖�Ǝ�́A�J�Еی��ɉ������Ȃ���Ȃ�܂���B �����P�V�N�P�P���P������J�Еی��������̎��Ǝ�ɑ����p�������啝�ɋ�������܂��B �J�Еی��̉����葱�����s��Ȃ��������ԂɘJ�Ў��̂����������ꍇ�A�k���ĕی��������������ق��A�J�Еی��̋��t���̂P�O�O���܂��͂S�O�������Ǝ傪���S���邱�ƂɂȂ�܂��B �@ �k��p�����̓��e�l �@�P�D�̈ӂɎ葱���s��Ȃ����Ǝ�E�E�E�J�Ћ��t���̂P�O�O�������i���݂S�O���j �@�@�@�s���@�ւ�������w���������ɂ�������炸�����葱�����s���Ă��Ȃ��� �@�Q�D�d��ȉߎ��Ŏ葱���s��Ȃ����Ǝ�E�E�E�J�Ћ��t���̂S�O�������i���K��Ȃ��j �@�@�@�����w�������Ă��Ȃ����A�����`�����������Ă���i�J���҂��ق��Ă���j�P�N�ȏ� �@�@�@�����葱�����s���Ă��Ȃ��� �@ ����̉����ɂ�薢�������Ǝ�̂ւ̔�p�����͔��ɑ��z�ɂȂ�A�����w�����Ă��Ȃ����������Ǝ���ΏۂƂȂ�܂��B���ݖ������̎��Ǝ�l�͑��߂ɉ����葱�����s���Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz�Œ���������肳��܂���(�g�P�V�j �@�����P�V�N�P�O����茧�̍Œ���������Ԋz�V�P�Q�~�ɉ��肳��܂����B �����̏�p�E�Վ��E�p�[�g�E�A���o�C�g���S�Ă̘J���҂ɓK�p����A���̋��z�ȏ�̒������x�����K�v������܂��B���^�v�Z�Ȃǂ̍ۂ͏[�����ӂ��Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�����N���z�����N���ی��̕ی��������肳��܂� �@�����P�V�N�X���������N���̕ی������O�D�R�T�S�������グ���܂��B ������肳�ꂽ�����N���̕ی����́A�����P�V�N�X�����i�P�O���[�t���j���畽���P�W�N�W�����i�X���[�t���j�̕ی������v�Z����ۂɎg�p���܂��B���^�v�Z�Ȃǂ��s���ꍇ�ɂ͒��ӂ����ĉ������B �@ �@��ʔ�ی��҂̏ꍇ�E�E�E �@�����P�V�N�W���܂ŁG�P�O�O�O���̂P�R�X�D�R�S�@�A�@�X������G�P�O�O�O���̂P�S�Q�D�W�W �@ �������P�U�N�̉����ɂ��A�����N���ی��̕ی������́A�����P�U�N�P�O�����i�����P�V�N�x�ȍ~�͂X�����j����A���N�A�O.�R�T�S���i�D���E�B�����ɂ��Ă͂O.�Q�S�W���j�������グ���A�����Q�X�N�X���Ȍ�͂P�W.�R���ɌŒ肳��邱�ƂɂȂ�܂����B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�����P�V�N�Z���b�͂̒�o�ɂ��� �@�Љ�ی��̕�V���z�Z���b�͂̒�o�����ƂȂ�܂����B �Ώۂ́A�����P�V�N�V���P�����݂̎Љ�ی���ی��ґS���ƂȂ�܂��B�i�U���̎��i�擾�҂������j ���łɎЉ�ی����������X������Ă��鎑�����Q�l�ɂ��Ă��������B �@��o�����͗X���̏ꍇ�͂V�^�P�P(��)�K���ƂȂ�܂��̂ŁA�x��Ȃ��悤�ɏ��ލ쐬�����Ĕ��� ���Ă��������B �@�Ȃ��A�S�N�̃T�C�N���ŎZ���b�͒�o���̎��Ə��������s���܂��B�����Ώۂ̎��Ə��� �Љ�ی�����������w�肳�ꂽ���@�Œ������Ă��������B�����ΏۊO�̎��Ə��������� ���ĂS�N�̂����ɒ����ΏۂƂȂ�܂��̂ŁA�͏o���̒�o�Y�����t���[�ނ̕s���Ȃǂ������� ���ɍ���x�_�������Ă݂Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�ܗ^�x���͒�o��Y��Ă܂��H �@�ܗ^���x�������Ƃ��͂T���ȓ��ɏܗ^�x���͂��Љ�ی��������Ȃǂɒ�o����K�v������܂��B �ܗ^�̎x�������I�������A�����Ɏx���͂̍쐬�E��o������悤�ɋC�����܂��傤�B ���łɏܗ^�x�����I����Ă��鎖�Ə��ɂ��Ă͎x���͂̒�o��Y��Ă��Ȃ����m�F���Ă݂Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�J����z��N�̈����グ�ɂ��� ���N��ғ��̌ٗp�̈��蓙�Ɋւ���@���̈ꕔ����������@�����������܂����B (1) ��N�̈��グ�A�p���ٗp���x�̓����� �@�U�T�Ζ����̒�N�̒�߂����Ă��鎖�Ǝ�͈ȉ��̂����ꂩ�̑Ή����K�v�ɂȂ�܂��B �@�@�@�U�T�܂ł̒�N�̈��グ �@�@�A�p���ٗp���x�̓��� �@�@�B��N�̒�߂̔p�~ �p���ٗp���x�͊��J�g����ɂ���߁A��]�ґS����ΏۂƂ��Ȃ��Ή����\�ł��B �@ ���N��Ҍٗp�m�ۂ̔N��(�U�T��)�́A�����Q�T�N�x�܂łɒi�K�I�Ɉ����グ���܂��B �@����18�N4���`����19�N3�� �F 62�� ����19�N4���`����22�N3�� �F 63�� �@����22�N4���`����25�N3�� �F 64�@ ����25�N4���`�@ �F 65�� �@ (2) ���E�����x�����̍쐬�E��t �@��Гs���̉��ٓ��ɂ�藣�E���鍂�N��ғ�(�S�T�Έȏ�U�T�Ζ���)����]����Ƃ��́A �@���̐E���̌o���A�E�Ɣ\�͓��̍ďA�E�Ɏ����鎖�����L�ڂ������ʁi���E�����x�����j�� �@�쐬���A��t���Ȃ���Ȃ�܂���B (3) ��W�y�э̗p�ɂ��Ă̗��R�̒� �@�J���҂̕�W�y�э̗p�ŁA����N��i�U�T�Ζ����̂��̂Ɍ���j���߂�ꍇ�ɂ́A���E �@�҂ɑ��ė��R�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�܂���B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�Љ�ی��z�e�c�Ȃǂɂ��͏o�����Ă��܂����H �@�Љ�ی��Ɋւ���e��͏o�ɂ��Ă͂e�c(�t���b�s�[�f�B�X�N)��l�n(�����C�f�B�X�N)�Ȃǂ̎��C�}�̂ɂ��͏o���o���܂��B�͏o���Ɏ菑���ŋL�������Ԃ��Ȃ��܂��̂ŁA��������Ă��Ȃ����Ə��ɂ��Ă͌�������Ă͂������ł����H �@�k���C�}�̂Œ�o�ł���͏o�l �@�@���i�擾�́A���i�r���́A��V���z�Z���b�́A��V���z�ύX�́A�Z���ύX�́A�ܗ^�x���� �@����Ɏ�Ԃ��Ȃ����߂ɁA�͏o�ɕK�v�ȏ]�ƈ��Ȃǂ̃f�[�^����͂����e�c���Љ�ی�����������Ƃ邱�Ƃ��o���܂��B���̕��@���^�[���A���E���h�����Ƃ����܂��B �ڂ����͊NJ��̎Љ�ی��������֖⍇�����������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�ٗp�ی��z�玙�x�Ƌ��t�E���x�Ƌ��t���ς��܂� �@�����P�V�N�S���P�����玙�x�Ƌ��t�E���x�Ƌ��t���ς��܂��B��ȕύX�_�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B �@ ���玙�x�Ƌ��t�E�E�E���Ԃ̉��� �@���܂Ŏq���P�ɖ����Ȃ����Ԃ��x���Ώۂł������A�ȉ��̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�͂P�Δ��ɖ����Ȃ����Ԃ܂őΏۂƂȂ�܂��B �@�P�D�ۈ珊�ɕۈ�̊�]�����Ă��邪���ʕۈ炪�s���Ȃ��Ƃ� �@�Q�D�玙�x�Ƃ̐\�o���������̔z��҂ŁA�P�ΈȌ�̗{��\��̕����ȉ��̂����ꂩ�ɊY������Ƃ� �@�@�i�P�j���S�����Ƃ��@�i�Q�j�����Ȃǂɂ��{�炪����ɂȂ����Ƃ� �@�@�i�R�j�������ɂ��q�Ɠ������Ȃ��Ȃ�Ƃ� �@�@�i�S�j�U�T�Ԉȓ��ɏo�Y�\��܂��͎Y��W�T�Ԃ��o�߂��Ȃ��Ƃ� ���玙�x�Ƌ��t�E�E�E���Ԍٗp�҂ւ̓K�p �@���Ԍٗp�҂ɂ��Ă����̗v�������ꍇ�͈玙�x�Ƌ��t�̑ΏۂƂȂ�܂��B �@ �����x�Ƌ��t�E�E�E������x�� �@���܂ŁA����Ƒ��ɑ��Ă͂P��̋x�Ƃ݂̂��Ώۂł������A�����Ƃ��ċ��t���̎x�������̍��v�����̓����ȓ��̏ꍇ�͕�����̎��\�ƂȂ�܂��B(�ڍחv���ȗ��j �����x�Ƌ��t�E�E�E���Ԍٗp�҂ւ̓K�p �@���Ԍٗp�҂ɂ��Ă����̗v�������ꍇ�͉��x�Ƌ��t�̑ΏۂƂȂ�܂��B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�ٗp�ی��z�ٗp�ی����������肳��܂� �@�����P�V�N�S���P�����ٗp�ی��������P�O�O�O���̂Q�����グ���܂��B �܂��A��ʕی����z�\�͂R���R�P���������Ĕp�~����܂��B��ی��҂���ی���������ۂɂ͒������z�ɐV�����ی��������悶�Čv�Z���܂��B�S���P���ȍ~�ŏ��̒������ؓ����ΏۂƂȂ�܂��B �k�ی������l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���^�v�Z�Ɩ����ϑ����܂��H �@���������ł͋��^�v�Z�����������Ă��܂��B �����̕ی����̌v�Z��ی������莞�̑Ή��ȂǂȂǂ��K�v�ł��̂ŁA���Z�������Ǝ�l�̕��S�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������悤�ł��B���������ł̓^�C���J�[�h�̂��a�肩�狋�^�����̂��n���܂Ŏ��Ə��ɂ��f�����܂��̂Ŗ{���̎��Ƃւ̕��S�͍ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��o���܂��B �@�Г��ŋ��^�v�Z�������s���Ă��鎖�Ə��������̂ł����A�]�ƈ��̃v���C�o�V�[�ɌW����e�ł��̂ŁA�g���u�����N���₷���Ȃ�܂��B�l���E�o���Ȃǂ̐��̕����������Ă����^�v�Z�����͊O���ɔC���Ă��鎖�Ə��������Ă��܂��B���p�ȃg���u��������邽�߂ɂ��o������苋�^�v�Z�͐��ƂɈ˗����邱�Ƃ��������߂��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڍׂ͂������ �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�����N���z�����N���ی��̕ی��������肳��܂��� �@�����P�U�N�P�O���������N���̕ی������O�D�R�T�S�������グ���܂����B ����ی����̌v�Z������ꍇ�ɂ͒��ӂ����ĉ������B �@��ʔ�ی��҂̏ꍇ�E�E�E �@�����P�U�N�X���܂ŁG�P�O�O�O���̂P�R�T�D�W�@�A�@�P�O������G�P�O�O�O���̂P�R�X�D�R�S �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz�Œ���������肳��܂��� �@�����P�U�N�P�O����茧�̍Œ���������Ԋz�V�O�W�~�ɉ��肳��܂����B �����̏�p�E�Վ��E�p�[�g�E�A���o�C�g���S�Ă̘J���҂ɓK�p����A���̋��z�ȏ�̒������x�����K�v������܂��B���^�v�Z�Ȃǂ̍ۂ͏[�����ӂ��Ă��������B �@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y��ʁz�Ð�s���J���������ɕς��܂��B �@�s�����m�Ð쎖�����Ƃ��ĉc�Ƃ��ĎQ��܂������A���̓x�w�Љ�ی��J���m�x�̓o�^���s���A�Ð�s���J���������Ɩ��̂�ύX���邱�ƂɂȂ�܂����B�@�J���ی��E�Љ�ی��̏��葱���ɂ��Ă��戵�����ƂɂȂ�܂��̂ŁA���܂ňȏ�ɕ��L���T�[�r�X�̒��s�Ȃ��Ă܂���܂��B �@���A���܂łǂ���A�^���ƁE���ƂȂǂ̋��F�Ɩ����p�����čs�Ȃ��܂��̂ł�낵�����肢�������܂��B �@�@�s�����m�Ɩ��ɂ��Ă͐�p�y�[�W�ɂĂ��m�F���������B�@���@�@�s�����m�̃y�[�W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||