|
|
| |
|
|
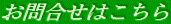 |
| |
社会保険労務士とは・・・
社会保険労務士とは、労働保険(労災・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)の
手続と人事・労務管理の専門家です。
|
ここ数年、巡回指導においても社会保険の加入有無の確認が追加され改善指導が行なわれて
いましたが、平成20年より処理方針を改正し未加入対策が強化されています。
『新規許可申請者への対応』
運輸開始までに社会保険等の加入が義務化されます。
平成20年7月1日以降の申請分運輸開始の条件に社会保険等(雇用保険・労災保険・健康保険・
社会保険)の加入が追加されています。
『既存許可事業者への対応』
巡回指導を通じて加入を指導するとともに、巡回監査において未加入が確認された場合は、
行政処分等を行なうことになります。
以前より法律上は加入義務がありましたが、金銭的な面で加入していない方もいらっしゃいます。
今後の運送業界では加入しないわけにはいかなくなります。
月々の負担は増加しますが、従業員が安心して働ける環境を確保するためにも加入は必要です。
事業主側から見ても、有能な人員の定着やいざというときの保証というメリットもあります。
運送業をメイン業務とした行政書士と、社会保険などの労務手続き行なう社会保険労務士を兼ねた
当事務所へのご依頼は、業務上の安心と経理上の負担軽減をお約束します。
|
今後の提案をいたします
当事務所では貴社の発展のために次のような提案をいたします。
1.許認可の取得および維持
2.労働環境の整備
|
許認可の取得および維持
必要な許認可の取得はできていますか?
今まで安定した利益確保の手法としての許認可の取得をご案内し、多くの賛同を頂きました。
今後も業務受注の拡大を考えた場合、許可業者?無許可業者の関係は更に強まると思います。
今まで無許可でも以前からの付き合いもあり依頼をされていたケースが、今後は無くなってきます。
最近の法改正の流れでは発注者にも許可業者への発注義務が強化されています。
今年施行された『自動車リサイクル法』を例にとると、許可・登録業者以外は業を行なえず、無許可
業者へ依頼した側へも罰則が課せられています。今後もこの傾向は続いていくでしょう。
当然発注者もシビアになり受注先を徹底して比較することになるでしょう。
実質、無許可業者は生き残れない仕組みとなっています。
負け組とならないよう必要な許認可は確実に取得しましょう。
必要な許認可としては・・・ |
・軽貨物運送業の方や運送業の許可のない方は、一般貨物運送業許可を取得する。
許可要件も必要車両数の減少・車の耐用年数の緩和など、取得しやすくなってきています。
・貨物運送業に関連する許可を追加取得する。
利用運送事業を取得する。他の運送業者の運送を使って運送業務を行う事業。
法改正でトラックを使う第一種利用運送は許可→登録制になり参入が容易になりました。
倉庫業の登録を行なう。荷物の運送だけでなく、保管業務も加え定期収入を確保できます。
倉庫業は許可から登録制になり要件等も緩和されました。
・旅客運送業の許可を取得する。
旅客運送業の許可を取得する。注目の介護タクシー(患者輸送サービス)の制度が改正され、
車両台数が1台から開始でき、新規に参入される方も多くなっています。
・産業廃棄物処理業(収集運搬)の許可を取得する。
運送業における新規事業の展開としては一番多い許可です。環境問題が話題となる昨今、
注目される業種です。(今後確実に取得が厳しくなってきます。取るなら今です。) |
|
| |
許認可の維持が今後は重要!
様々な分野で規制緩和が行なわれ、許可の取得・新規参入は容易になってきています。
今後は事後チェックの時代であり、許認可の維持が重要です。
許可は取らせるが、何か問題があれば許可の取消しを行なう。いい加減な管理体制・事務処理を
行なう事業者は許可の維持が出来なくなってきます。
許可の基準を遵守する体制も必要ですし、手続がわからない・時間がとれない方は専門家への
外注を考えてください。
許可が無くなってから慌てても遅いのです。
必要な手続きとしては・・・(貨物運送業の例) |
・事業実績報告、事業報告
毎年報告義務があります。事業実績報告は〜7/10、事業報告は決算後100日以内。
・営業所、車庫の移転認可
営業所や車庫の移転・変更をする場合は事前に変更認可を受けなければなりません。
手続きを忘れ行政処分を受ける事例が多いので気をつけてください。
・会社役員の変更届出
代表取締役はもちろん一般役員の変更時も届出が必要です。 |
|
| |
労働環境の整備
従業員の定着率は大丈夫ですか?
今までは対外的(対お客様)についてお話しましたが、これから先は会社内にも目をむけてください。
従業員が定着しないような会社では今後の発展も望めません。
職場環境の整備と適正な人員配置を行い、従業員が安心して働けるようにしなければなりません。
労働保険・社会保険への加入は法律だから仕方なくではなく、従業員のために必要なのです。
労働環境を向上する手段として労働保険・社会保険の加入は最低条件だとお考え下さい。
また、保険手続などの事務手続きは出来るだけ外注にし、有能な人材を有効に活用してください。
必要な手続としては・・・ |
・労働保険(労災・雇用保険)手続き
新規加入手続、被保険者資格取得・喪失手続、年度更新手続、休業給付手続
・社会保険(健康保険・厚生年金)手続き
新規加入手続、被保険者資格取得・喪失手続、算定基礎届、月額変更届、年金給付手続 |
|
| |
専門家に頼むのにはお金がかかる!とお思いの方も多いと思います。
自分でやればタダと思う方もいらっしゃいますが、人件費として考えてみればタダではないのです。
しかも慣れない事務手続は事業の拡大にはなんら寄与しません。
事務手続きなどについては他人でも出来ますが、事業の展開は社長(取締役)など会社を管理する
立場の人にしか出来ないのです。
管理者が本来の会社管理を行ない、事業の拡大維持に全力を傾けて頂きたいと思います。
利益を確保する為に、効果のでるところに投資をする。
アウトソーシングにより専門家をうまく使いこなしてみてください。
当事務所では、あなた様と一緒に成長していきたいと考えています。これを機にご一緒に仕事を
させて頂けるようになれば光栄です。
|
 |
|
|